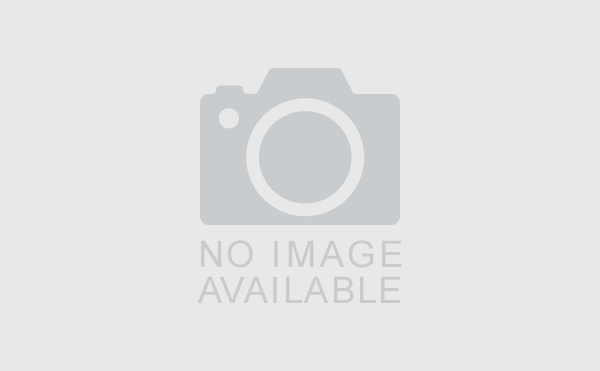能登半島地震災害復旧・復興状況調査 3日目
能登半島地震災害復旧・復興状況調査3日目は盛本芳久石川県議と合流し、石川県庁にて災害関連の担当の方から震災と豪雨災害の状況、復興に向けた取り組みについて説明を受けました。その内容です。
石川県の災害対応について
・能登半島は平地が少なく、地滑りが多い。能登6市町は高齢化率が軒並み50%近い。
・のと里山街道が能登の動脈。別所だけ付近が寸断された。日々、状況はよくなっている。
・海岸線、国道249号線は重要。海沿いの幹線道路が土砂崩れで寸断し、孤立集落が発生した。その後、海沿いのもともと海であったところに道路を通した。
・輪島の朝市の火災について。建物倒壊と川の隆起で水を確保できなかった。
・地区のコミュニティ維持のため、集落のまるごと避難が実施された。
・現在は1次避難所の避難者は11名。3月で0になる予定。
・川が短くて急なため、9月の豪雨被害では、普段とびこえられる川が氾濫した。
・経験則にとらわれない防災対策が必要。
創造的復興について
・仮設住宅には従来のプレハブ型のほか、木造長屋、木造戸建て風がある。
・断水は解消されているが、屋内配管がまだ復旧していない家もある。輪島で382戸、珠洲で309戸。
・国の制度で公費解体が進められており、半数くらいが解体完了。
・「なりわい再建補助金」で現状復帰の3/4が措置される。店舗の営業は80%再開している。
・創造的復興プランが9年間の期間で計画されている。
・県庁内だけでなく外部有識者も参加するのと未来トークが8回開催されている。
・「能登らしさ」を最も大事にしたいと考えている。「壮大な自然が織りなす類稀な絶景と豊かな生命」など4項目。
・地域が考える地域の未来を尊重することなど12項目の基本姿勢の提示が示されている。
質疑応答です。
Q1 国の現地に対する主導体制とのギャップをどう埋めた?
A1 被害想定は難しい。もともと持っていた被害想定は20年前につくったもの。2019に能登半島地震を一度経験しており、これを踏まえて防災対策を進めていた。ここまでは想定していなかったのが実態。物資の備蓄について、想定より多くのものを準備するという基本姿勢。現物だけでなく、流通備蓄も行っていたが、流通が相当やられてしまった。国と他の地域の支援は早くスタートできている。問題は、被災地に迅速に届けること。被災地の拠点までは届けることができたが、その先の供給は大きな課題。道路の損壊、マンパワーの問題など課題として残る。孤立集落、道路をできないため自衛隊の隊員が道なき道を物資を運ぶという事もあった。想定は大事だが、想定と現実のギャップは発生する。近隣の市町に避難することは全国でも想定されているが、圏域を超えて避難する想定はしていなかなかった。今後の課題。
Q2 一次産業が壊滅的だがどのように復興する?
A2 農林水産業の設備の復旧が課題。一つは土地、港などのインフラ。輪島港は一大拠点だったが使えない状態まで隆起している。半年かけて浚渫してカニ漁には間に合わせる。外浦など小さい港は復旧できないため、輪島、七尾に移動して水揚げする。農業は、豪雨の被害。土砂立木。土壌の変化。ある程度は農水省で対応している。400~500haの被害、1年で復旧は150ha。補助金で何とかやっているが農家はまだ再開できていない。今回、農林漁業のお手伝いをする農林ボランティアが活躍している。数千人単位。農家にとっては、お金も大事だが、現場作業として助かったとの声があった。
Q3 初動が大事だが、備えについては?
A3 まず、ご家庭での備蓄のための普及啓発。通信が途絶することへの備え(衛星携帯などを市町で準備することが必要)。できる部分については自立型のインフラを整備していく。
Q4 県警との連携は?
A4 警察、消防、自衛隊と連携している。いかに迅速に情報を共有するか、現場がスムーズに動けるようにするかが課題。
Q5 仮設住宅について
A5 能登はかわら屋根多いが、耐震性をもっている住宅は瓦屋根でも倒壊していない。いちばんの備えは耐震で、50~60年前の家は耐震補強することをすすめている。
災害復旧の中で、制度趣旨を踏まえ、修繕の際の耐震強化を進めている。仮設住宅については、国とも協議しながら戸数を立てている。震災と豪雨災害は分かれており、震災の仮設住宅が空いてきているところに豪雨被害の方を入れている。震災で、3世代住んでいる住宅を分けて住めないかなど、住んでいる人のニーズを考えながら対応している。豪雨被害の方の住宅の戸数の完成が見えてきた。仮設住宅は2年で、仮の住まいで移ることが前提。しかし、一度住むと、移るの大変で住み続けたいという希望もある。仮設を住宅を建てる場所は、効率性だけでなくコミュニティの復興も考慮している。
Q6 仮設住宅の居住権や家賃について
A6 仮設住宅の期間が過ぎ、市町の施設として使うと市町に負担が発生し、有償となる。
Q7 消防は自治体職員だが、職員も被災している。職務専念義務との線引きは?
A7 被災者、罹災証明をもらったら休めるというものでもないが、通常の勤務は難しいため、そのことについて配慮ある。県内のほかの市町からの応援、他県からの応援職員も入っており、その方々の手助けがなければ被害認定調査も進まなかった。
限られた時間ではありましたが、能登半島地震及び奥能登豪雨被害の状況や、その後の復興に向けた取り組みについて理解する
非常に有意義な意見交換となりました。盛本県議、石川県庁の担当のみなさまに感謝申し上げます。